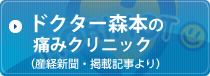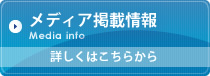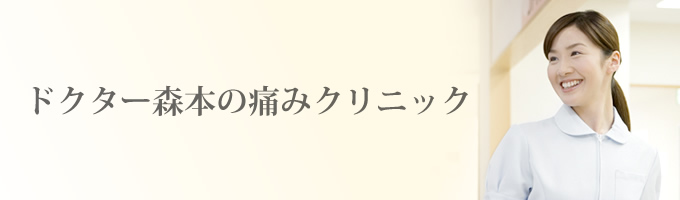Dr. Morimoto’s pain clinic ドクター森本の痛みクリニック
97 無痛分娩
ストレスは妊婦、胎児にも影響
「産みの苦しみ」との言葉がある。この言葉の通り、女性が分娩(ぶんべん)の際に経験する痛みは、他の多くの痛みよりもはるかに強い。さらに痛みによるストレスは、妊婦のみならず胎児にも多大な生理的影響をもたらすことから、痛みを軽減する意義は大きい。
分娩は三つの時期に分けられる。陣痛が始まってから子宮口全開大までの第一期には子宮の下部が伸展することで間歇(かんけつ)的な痛みが生じる。第二期(娩出期)になると、膣、会陰部の痛みが加わり、胎児が娩出されるころには持続的な痛みとなる。胎盤が排出される第三期にも、会陰部の痛みが残される。
以上の分娩経過に伴う痛みを緩和する方法を「無痛分娩」と呼び、さまざまなアプローチが考案されてきた。心理的無痛法、鎮静薬や麻薬、吸入麻酔薬の使用などである。しかし、ここでは妊婦が眠ることなく赤ちゃんの産声を聞くことができて、胎児への影響が少ない方法が要求される。
これらの点をクリアするのが「硬膜外麻酔」である。痛みを緩和するだけではなく、不安や緊張を軽減して子宮の過度の緊張を抑制することが利点である。通常は低濃度の局所麻酔薬が注入されるが、これに少量の麻薬(フェンタニル)を添加することでその効果はより確実なものとなる。
無痛分娩の歴史は古い。ペルシャの書物には、伝説の英雄が妊婦にワインを与えて分娩を容易にしたとする記述がある。一方で、宗教的理由により弾圧を受けた時期も存在した。しかし、一八五三年に、英国の麻酔科医スノーが、ヴィクトリア女王がレオポルド王子を出産する際に、クロロホルム麻酔を行ったことで、無痛分娩の是非を問う論争に終止符が打たれた。
現在、北米やヨーロッパ各国では90%以上の施設で無痛分娩が行われているが、わが国での普及率は低い。これはわが国の麻酔科医不足もさることながら、「おなかを痛めた子」との言葉に代表される“おしん”を尊ぶ国民性が悪い方向に影響しているとも考えられる。
(森本昌宏=近畿大麻酔科講師・祐斎堂森本クリニック医師)