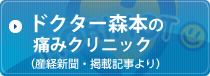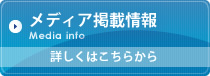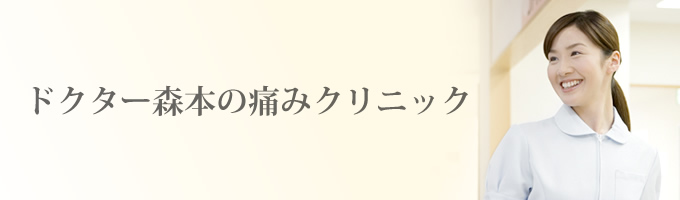Dr. Morimoto’s pain clinic ドクター森本の痛みクリニック
25 慢性痛
「病気を治せば消える」勘違い
手足をぶつけた、指を包丁で切った、火傷(やけど)を負った、などで生じる「急性痛」は、身のまわりの危険から私たちを守ってくれる警告信号である。一方で、私どものペインクリニックを訪れる患者さんを悩ませ続けている「慢性痛」はそうではない。慢性痛は、急性痛とは異なり、百害あって一利なし、警告信号が鳴り続けているだけで極めて無用なものである。
急性痛を「痛みの原因がなくなれば、消失する痛み」とするならば、慢性痛は「痛みの原因がなくなっても、消えない痛み」と定義付けられる。この定義に従えば、急性痛がいくら長期間にわたって続いても、それは慢性痛にはなり得ないのだ。換言すれば、痛みの原因がなくなっていない場合の痛みは急性痛なのである。つまり、急性痛と慢性痛とは同じ痛みであってもその成り立ちはまったく異なるのだ。
慢性痛は、末梢(まっしょう)神経や中枢神経系への持続的な刺激、温覚や触覚の異常によって生じ、自律神経系の異常を引き起こして、痛みに対する感受性を強くする。さらには、不眠、食欲不振、意欲の低下などを起こす。これらによって、人は自分の殻のなかに閉じこもってしまうことも多い。従って、慢性痛は単なる病気の症状のひとつではなく、それ自体が独立した症候群と考えたほうがよいだろう。
米国では、国民の約三分の一が慢性痛を有し、約六千万人が日常生活を制限されている。その医療費を含めた経済的損失を試算すると、年間六百億㌦(約七兆円)にも達する。つまり、慢性痛は個人的のみならず、大きな社会的損失をもたらしているのだ。慢性痛から多くの人たちを解放することは、国家レベルでの命題と言える。米国のクリントン前大統領が、2001年からの十年間の医学の主テーマを「Decade of Pain Control and Research」と宣言したことは、これを裏付けている。
これまで、痛みは病気の症状に過ぎない、病気を治せば痛みも自然にとれるはずだと考えられてきた。医師たちでさえそう考えていたのだ。この勘違いこそが、慢性痛への対策を遅れさせてきた大きな原因なのである。
(森本昌宏=近畿大麻酔科講師・祐斎堂森本クリニック医師)